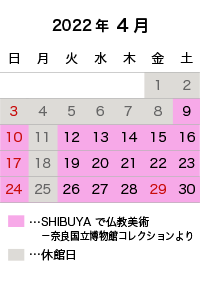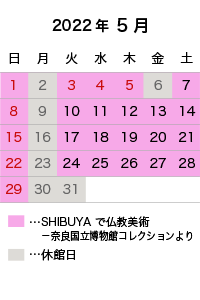うす暗い街燈や蠟燭から、明るいランプに移る明治時代、それは、庶民にとり、最も身近に感じられる新しい日本の夜明けだった。そして、明治一代の間に、石油ランプ・瓦斯燈・電燈へと燈火は急速に発達する。
明治初期には、江戸時代にひきつづき、燈火の主流は、燭台・行燈であり、さらに貧しい燈火として「ひで」と呼ばれる松の根などを燃やすひでばちなどが用いられ、旅行用には小田原提燈・懐中燭台などが使われた。
そして、この頃、油を用いる日本独自の燈火器として、田中久重・大隈源助が発明した無盡燈と呼ばれる一種のランプがあった。しかし、これらの燈火器は、石油ランプの登場により漸次駆逐されていった。芥川龍之介の『雛』という小品に、「その晩の夕飯は何時もより花やかな気がしました。それは申す迄もございません。あの薄暗い無盡燈の代りに、今夜は新しいランプの光が輝いてゐるからでございます。兄やわたしは食事のあひ間も、時々ランプを眺めました。石油を透かしたガラスの壺、動かない焔を守った火屋―さう云ふものの美しさに満ちた珍らしいランプを眺めました。」とある如く、ランプの明るさは、それ自体が美であり、驚きでもあったのだ。このランプも、当初は輸入されていたが、国内での製造が可能になると、日本の生活様式や和室に適した行燈ランプ・竹台ランプ・箱台つきランプなどの独自の工夫も加えられていったのである。また、欧米よりもたらされた美しいガラスの笠をもったランプが上流の人々の間にもてはやされ、それを模した日本製の笠が作られるなど、近代硝子工業の興起にも、ランプの与えた影響は大きかったといえる。
この石油ランプを並行する形で、瓦斯燈が用いられた。その青白い光は、北原白秋・芳井勇らにより詠いあげられたのである。しかし、瓦斯燈の命は短かく、明治11(1878)年のアーク燈の試験点燈の成功に始まる電燈の普及により、瓦斯燈はそのシェアを漸次奪われ、明治末のタングステン電球の発明により、その使命は終わり、以後、今日に至る電燈の時代となったのであった。
展覧会情報
| 会期 | 1983年9月6日(火)1983年10月23日(日) |
|---|---|
| 入館料 | 一般200円 小・中学生100円 |
| 休館日 | 毎週月曜日(ただし、第2週のみ日曜日)祝日の翌日及び年末年始(12月29日~1月3日) |
| 主催 渋谷区立松濤美術館
併催 特別陳列 渋谷区在住作家の作品 | |

展覧会図録
完売